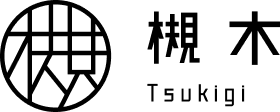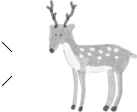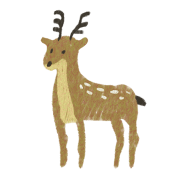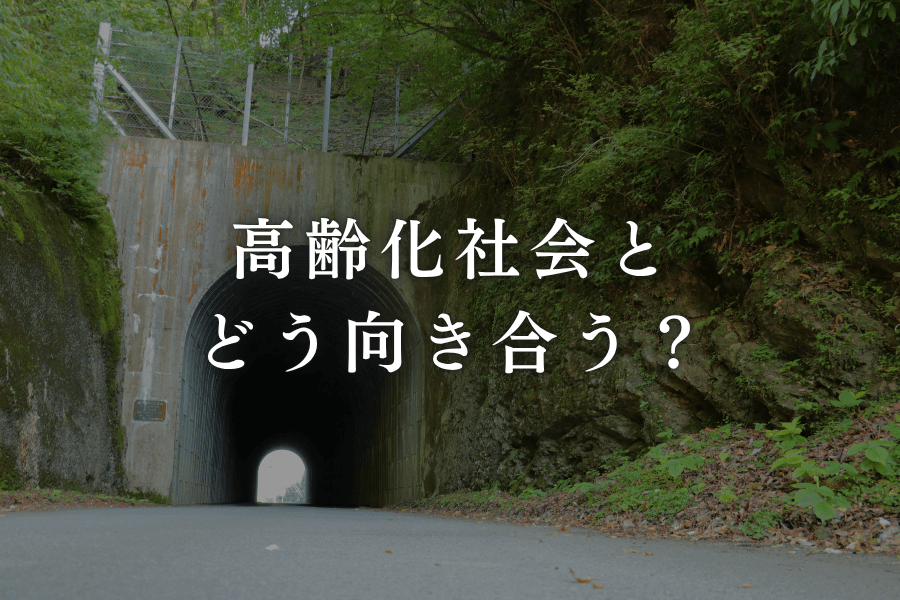「高齢化社会」という言葉、よく耳にするけれど、具体的に何が問題で、私たち若者にはどんな関係があるのでしょうか?年金や医療の不安、人手不足、そして地域社会の変化…。日本の未来を考える上で避けては通れない課題です。
この記事では、高齢化社会の現状と背景、そして若者の世代に直結する具体的な問題点をわかりやすく解説します。
さらに、これらの課題にどう立ち向かうべきか、解決策や取り組み事例もご紹介。未来のためにいま知っておくべきこと、そして私たちができることを一緒に考えていきましょう。
高齢化社会って何?まず知っておきたい基礎知識
ご存知の通り日本はまさに高齢化社会。まずはいま日本で何が起きているのか、その現状と背景を見ていきましょう。
日本の高齢化の「今」

日本は世界でも類を見ない速さで高齢化が進んでいます。
高齢化(または高齢化社会)とは、総人口に占める65歳以上の人の割合がどんどん高まっている社会のこと。2024年時点では日本の総人口の約29%が65歳以上で、これは約3人に1人が高齢者という計算です。
この割合は今後もさらに増え続けると予測されており、私たちの生活にも大きく影響することが予想されています。特に地方では若者の都市部への流出も加わり、高齢化がさらに加速している地域が多く見られます。
単に「おじいちゃん、おばあちゃんが増える」というだけでなく、社会の仕組み全体に大きな変化を迫る問題なのです。
なぜ進む?高齢化の背景

日本の高齢化が進む主な理由は2つあります。
1つは、医療の進歩や生活水準の向上により、多くの人が長生きできるようになったこと。これを「平均寿命の延伸」と呼びます。
例えば、1950年には男性の平均寿命が58歳、女性が61歳でしたが、現在では男性が約81歳、女性が約87歳と大幅に伸びています。
もう1つは、子どもの出生数が減っていること、つまり「少子化」です。かつては1人の女性が生む子どもの平均が2人を超えていましたが、現在は1.2人台(2023年時点)と過去最低水準が続いています。
長生きする人が増える一方で、新しく生まれる命が減る。この2つの要因が重なることで、日本の高齢化は加速的に進行しているのです。
若者にも関係大!高齢化社会の具体的な問題点
高齢化社会は、将来を担う私たち若者にこそ深く関わる問題です。ここでは、特に重要な4つの具体的な問題点を掘り下げていきましょう。
1. 社会保障の危機:年金・医療・介護の今後
 高齢化が進むと、社会保障制度に大きな負担がかかります。
高齢化が進むと、社会保障制度に大きな負担がかかります。
年金問題では、高齢者を支えるための現役世代からの保険料が減り、将来の給付額が減る、あるいは受給開始年齢が引き上げられる可能性があります。
医療費も高齢者の増加とともに増大し、若者世代の保険料や税負担が増える原因となります。さらに、高齢者が必要とする介護サービスも増え、その費用は私たちの社会全体で支えることになります。
これらの問題は、私たちが将来安定した生活を送る上で、見過ごせない課題となるでしょう。
2. 働き手不足と経済への影響

高齢化は、社会全体の働き手不足を深刻化させます。
生産年齢人口(15歳〜64歳)が減少し、経済を支える力が弱まるのです。労働力不足は企業の成長を鈍らせ、ひいては私たちの賃金や雇用機会にも影響を与える可能性があります。
例えば、人手不足でサービス業の営業時間が短縮されたり、地方では商店が減ったりするなどの具体例も出てきています。また、市場が縮小することで消費活動が停滞し、経済全体の活力が失われるリスクも考えられます。
3. 地域社会の変化:消えるつながり、増える課題

地方では若者の流出と高齢化が同時に進み、地域社会の基盤が揺らいでいます。
過疎化が進むと近所のつながりが希薄になり、共同での行事や防災活動が難しくなるなど、地域社会の維持自体が難しくなります。
限界集落(※)では、買い物や病院への移動手段がなくなる「買い物弱者」「医療難民」といった問題も発生し、日常生活すら困難になるケースもあります。
また、これは単に人が減るだけでなく、地域で培われてきた文化や伝統が失われることにも繋がりかねません。
※「限界集落」は地方創生において大事なキーワード。下記のページでしっかりと理解しましょう!
4. 高齢者の暮らしと生活課題

高齢者自身が直面する課題も多岐にわたります。
健康面では、慢性疾患や認知症が増え、長期的な医療や介護が必要になるケースが増加します。
しかし、施設やサービスの不足、あるいは経済的な理由から、十分なサービスを受けられない人も少なくありません。
また、高齢者の孤独死や、詐欺などの犯罪に巻き込まれるケースも増えており、安心して暮らせる社会の構築が急務です。運転免許の返納後、移動手段がなくなる高齢者の「交通弱者」問題も、地方を中心に深刻な問題となっています。
高齢化社会の課題にどう立ち向かう?具体的な解決策と取り組み事例
高齢化社会の課題は大きいですが、国や地域、そして私たち一人ひとりが対策を講じることで、より良い未来を築くことができます。ここでは、具体的な解決策と取り組みの具体例を見ていきましょう。
政府や自治体が行う高齢化対策

政府や自治体は、多角的な高齢化対策を進めています。例えば、地域で医療、介護、住まい、生活支援を一体的に提供する「地域包括ケアシステム」の構築は、住み慣れた地域で最期まで安心して暮らせる社会を目指すものです。
また、高齢者の労働参加を促す「高年齢者雇用安定法」の改正や、医療・介護費抑制のための予防医療の推進なども行われています。
地方自治体では、高齢者向けのコミュニティバス運行や空き家を活用した高齢者向け住宅の整備など、地域の実情に合わせた様々な取り組みが行われています。
地域で生まれる新たな支え合いの形

地域社会では、行政だけでなく住民自身が主体となった新たな支え合いの形が生まれています。
高齢者と若者が交流する「多世代交流カフェ」や、地域住民がボランティアで高齢者の生活支援を行う「NPO法人」の活動などがその具体例です。
買い物代行や見守り、子育て支援と高齢者支援を組み合わせた地域コミュニティなど、様々な工夫が凝らされています。これらの活動は、地域の「つながり」を再構築し、高齢者の孤立を防ぎ、同時に若者の社会参加を促す良い機会にもなっています。
テクノロジーが描く未来の高齢社会

最新のテクノロジーは、高齢化社会の課題解決に大きな可能性を秘めています。
例えば、高齢者の見守りや服薬管理をサポートするIoTデバイス、遠隔で医師の診察が受けられるオンライン医療システム、自動運転技術を活用した移動支援サービスなどが開発・実用化され始めています。
AIを活用した介護ロボットは、介護現場の人手不足解消に貢献することが期待されています。これらの技術は高齢者の生活の質を高めるだけでなく、医療・介護従事者の負担軽減にも繋がり、より効率的で質の高いサービス提供を可能にするでしょう。
まとめ:若い私たちが未来のためにできること
高齢化社会の問題は、遠い未来の話ではありません。私たち若者が「高齢化社会」という問題を自分ごととして捉え行動することが、明るい未来を築く第一歩となります。
まずはこの社会が抱える問題について知ること。そして、地域活動に参加したり、ボランティアをしてみたり、身近な高齢者との交流を大切にしたりすることで、新たな解決策のヒントが見つかるかもしれません。
将来の進路を考える際にも、高齢化社会がもたらす変化を意識し、社会貢献できる仕事やスキルを身につけることも、私たち若者ができることの一つです。
私たちの世代が主体的に関わることで、日本はもっと豊かで、みんなが安心して暮らせる社会へと進化していくでしょう。
※当サイトでは他にも地方創生について考える記事を更新しています。興味のある方はぜひご覧ください!