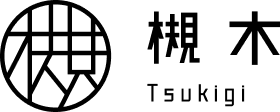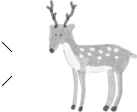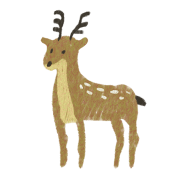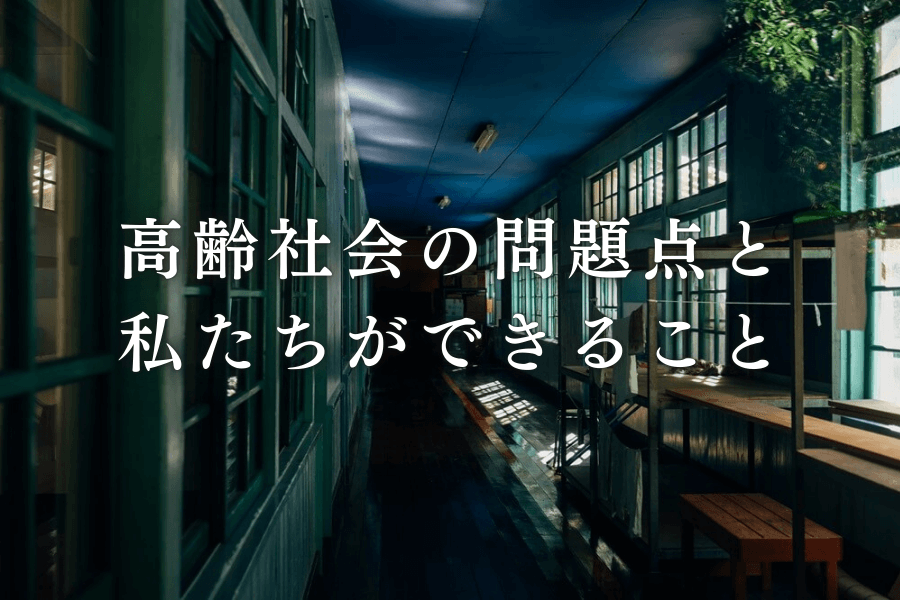少子高齢化。
このキーワードは、日本が抱える社会課題の中でも、特に大きなウエイトを占めている問題です。
少子高齢化によって起こる負の影響は、地域インフラの衰退、単身世帯の増加、伝統文化の継承困難など、多岐に渡ります。
当サイトで紹介している熊本県球磨郡のつきぎ集落も、人口は80人を下回り、最低年齢が60歳という「限界集落」にあたる地域であり、高齢化による多くの課題を抱えています。
今回は実際に超高齢社会の現状と対峙しているつきぎ集落の実例をもとに、高齢社会の問題について考えていきます。
高齢社会が加速する日本の現状

多くの方がご存知だと思いますが、現在日本は深刻な少子高齢化の課題を抱えています。
日本の高齢化率(65歳以上の人口が総人口に占める割合)は約29%となっており、これは超高齢社会という区分に該当します(※1)。
高齢化率7%を超えた社会を「高齢社会」といい、日本は1997年に高齢社会となりました。それから10年も経たないうちの、2007年に27%以上の高齢化率を指す「超高齢社会」に突入したということで、少子高齢化が著しく速いスピードで進行していることがわかります。
高齢社会で起き得る課題、問題点については後述しますが、今後日本ではさらに人口減少と高齢化が進むことが予想されており、2070年には総人口9000万人以下、高齢化率は39%の水準になることが推計されています(※2)。
高齢化の進行が確実視されている今、今後は高齢社会の中でお互いに支え合い、協力し合いながら生きていくことが非常に大切になります。
※1:総務省による、2024年1月1日時点の確定値のデータをもとに算出しています。
※2:厚生労働省の統計データを参照しています。
高齢社会が抱える課題、今後起こり得る問題

まずは、高齢社会となった国、地域が抱える課題や問題点について見ていきましょう。
高齢社会が引き起こす問題は、本当にたくさんあります。ここではその一部をご紹介していきます。
社会保障制度のひっ迫
高齢化が進むことにより、医療費や介護費といった社会保障費が急増することが懸念されています。
年齢を重ねるごとに、医療や介護の必要性が高まることは想像に難くないでしょう。しかし、これらの社会保障には当然予算が必要となります。
国や地方自治体が社会保障を負担しますが、もちろん予算は無限にあるわけではありません。予算が足りなければ、提供できるサービスの質も規模も悪化、低下してしまい、支援を必要とする人に適切なサービスを提供することができない場合が想定されます。
働き手の不足
高齢者の割合が増加し、働き手が減少することで、経済活動に支障が出る可能性があります。
高齢になればなるほど仕事に従事できる人の割合は低くなるため、人口減少と高齢化の課題を抱える日本においては、働き手の総数が著しく減少してしまいます。
また、特に介護や医療などの分野では増加する患者数に対して働き手が増えない、むしろ減少してしまう現状があるため、人材不足はより深刻な問題となっています。
働き手が足りなければ、サービスの低下や利用者の負担増が懸念されます。
地域コミュニティの衰退
地域サービスや施設の縮小・撤退、地域イベントの廃止などが余儀なくされ、地域コミュニティの衰退が進む可能性が考えられます。
社会保障制度の問題と同じく、人口減少は国や自治体の収入源の減少にもつながり、従来のサービスやイベントの実施、継続は難しくなります。
地域コミュニティは生活の支えや生きがいとなり得る重要な存在です。この地域コミュニティの運営が難しくなり、衰退が進行することは大きな問題だと言えます。
その他多数の問題点が考えられます
その他にも、高齢社会は様々な問題を引き起こします。
例えば、以下のような課題点が想定されます。
- 年金制度の破綻
- 防災・減災対策の難化
- 詐欺・虐待の増加
高齢社会が引き起こす問題は個別に発生するものではなく、連鎖的に複数の問題が生じます。そのため、何か一つ対策を行えばOKではなく、多角的な視点でのアプローチが重要となります。
【事例】つきぎ集落で実際に起きている課題
ここまでで紹介した高齢社会の問題点は、他のメディアでも取り上げられていることであり、耳にしたことがある人も多いと思います。
ただ、実際に起きている具体的な現状に触れないと、なかなか高齢社会の現状について実感が沸かないということもあると思います。
ここでは、人口80人以下、最年少が60歳の限界集落(※)、「つきぎ集落」に焦点を当て、高齢社会が作り出す実際の状況をお伝えしていきます。
※限界集落:人口比率の50%以上が65歳以上の地域
地域インフラの衰退

つきぎ集落は熊本県球磨郡の人里離れた山奥に位置します。買い物や通院のために町に出るためには、車で40~50分程度車を走らせなければいけません。
高齢者の多いつきぎ集落では運転免許証を持たない方も多いのですが、以前は走っていた町への往復バスは今は廃止となっています。
現在は乗り合いタクシーという形で、少ない本数で町への送迎が行われていますが、公共交通機関がないのは大きな問題です。
人が少なく、働き手もいないため、交通機関を整備することが難しいのです。
単身世帯の増加

つきぎ集落では、地域全体の半分近くを単身世帯が占めています。
単身世帯では、体に異常があった場合などに気が付いてくれる人が身近にいない可能性があり、このケースは特に高齢者の方にとっては命に関わる問題となります。
現在は集落支援員の方が安否確認を含めた自宅訪問を定期的に行っていますが、それでも突発的な体調不良などには対応することができず、十分ではありません。
地域の伝統、文化の継承が困難に

つきぎ集落には、地域独自の伝統的な文化や行事がいくつかあります。しかし、高齢化の影響もあり、これらの継承が困難になりつつあります。
つきぎ集落には「菅原神社」という歴史的な神社があり、毎年11月にはこの神社で例大祭が行われていました。しかし、コロナウイルスの影響もあり、現在は行われていません。
大切な地域の伝統文化、伝統行事がなくなってしまうというのも、高齢社会が抱える大きな問題の一つです。
高齢化に対して、私たちが今できること
高齢化を止めることができればそれがベストですが、決して簡単なことではありませんし、すぐにできることでもありません。
ただし、高齢社会の課題解決に少しでも繋げるための“行動”をすることは、今の私たちにもできます。学生も社会人も、性別も住んでいる地域も関係ありません。
行政や企業による取り組みだけでなく、私たち一人ひとりの意識や行動がとても重要です。
最後に、今の私たちにもできる、高齢社会への向き合い方や行動についてご紹介します。
ボランティアへの参加

高齢社会では人手が足りていないというのは、先述の通りです。しかし、ボランティアとして地域貢献活動に取り組む人は多くいます。
ボランティアには様々な仕事、取り組みがあり、ボランティア団体やボランティアサイトなどでは、多くの取り組みに対して募集が行われています。
また、ボランティア機関を利用せず、自分自身で地域のために活動をすることも、立派なボランティアです(※内容によっては許可が必要な場合もあります)。
高齢化が進行し、多くのサービスや支援の継続が困難になってきている今だからこそ、ボランティアはとても価値のある取り組みだと言えます。
地域コミュニティの活性化支援

こちらも先述の通りですが、特に高齢者にとって地域コミュニティは生活する上でとても大切なものになります。そんな地域コミュニティが、高齢化の影響で衰退していってしまうのは大きな問題です。
しかし、若者が中心となって地元のコミュニティに積極的に参加し、盛り上げようと行動することはとても意味があります。たとえコミュニティが衰退の一途にあったとしても、盛り上げることによってそこに参加する人たちに良い影響が与えられているのだとしたら、それはコミュニティとして素晴らしい形であると言えます。
これもボランティアの一種であるといえますが、身近なところからスタートできる行動の一例です。
高齢者への理解を深める

具体的な行動を起こすことができなくても、高齢者への理解を深め尊重する気持ちを持つことは、高齢社会への向き合い方として大切です。
高齢の影響で体に不自由がある方や、病気を患っている方に少しの手助けをすることは素晴らしい貢献です。
電車で席を譲ってあげるなど、小学生が教えてもらうようなことも実際に行動を起こすのは決して簡単ではありませんが、小さなことで大丈夫です。自分ができることから、初めてみましょう!
私たちができることはまだまだたくさんあります!
高齢社会の問題は深刻で、簡単に解決できるものではありません。ですが、だからといって黙って見過ごすわけにもいきません。
根本的な解決は政府や自治体の動きを注視するほかありませんが、今の私たちにもできることがたくさんあります。
どんなことでも、些細なことでもいいので、少しずつ自分のできることでこの高齢社会に貢献していきたいですね!
このサイトでは、地域創生について幅広い視野で考えていくというテーマで、記事を更新しています。ご興味をお持ちいただけた方は、ぜひ他の記事もご覧いただけましたら幸いです!