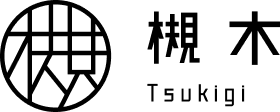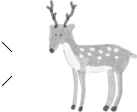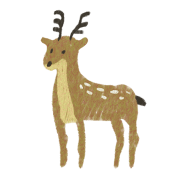球磨焼酎(くまじょうちゅう)。
それは人吉球磨が世界に誇る特産品であり、文化であり、魂でもある、重要な地域資源の一つです。
現状わかっている情報によると、その起源は室町時代にまで遡ります。もしかしたらもっと昔から親しまれている可能性も十分あります。
今回はそんな伝統ある球磨焼酎の歴史について解説していきます。
歴史・背景を知ることで、球磨焼酎が今よりももっと好きになるはず!ぜひ最後までご覧ください。
まずは球磨焼酎について

熊本県南部の人吉球磨地域で、500年以上にわたる歴史と共に育まれてきた伝統の米焼酎が、今回ご紹介する「球磨焼酎」です。
この土地には、焼酎造りに欠かせない豊かな自然の恵みがあります。

19年連続で水質日本一に選ばれた“川辺川”を含む球磨川水系の清らかな河川、そしてこの水源を活かして丹精込めて育てられる、コンクールでも入賞多数の良質な米。
地域の周りが山々で囲まれた盆地地域でもあり、これらの特徴が一体となることで、球磨焼酎ならではの奥深く、繊細で、上質な味わいが生まれます。
さらに人吉球磨地域には個性豊かな複数の蔵元が存在し、それぞれの蔵元が長年の経験と技術、そして情熱を注ぎ込むことで、驚くほど多様な個性を持つ球磨焼酎が生み出されています。

「鳥飼」や「大石」のような定番商品から、「銀しろ」や「カオル」といったカジュアルで人気の銘柄まで、そのラインナップは多岐に渡ります。
これらの球磨焼酎の特徴、魅力を生み出しているのは、冒頭で述べた「球磨焼酎500年の歴史」にあると言っても過言ではありません。
今回はそんな球磨焼酎の歴史について改めて調べてみたので、その内容をご紹介していきます!
球磨焼酎誕生のルーツと初期の発展
16世紀頃の記録と焼酎文化の普及
焼酎がいつ・どこで生まれて、どのように飲まれていたのか、などの情報が記載された資料はあまり残っておらず、正確な起源は明らかになっていません。
ただし、現在確認できる資料の中で一番最初に「焼酎」の文言が登場するのは、鹿児島県大口市の郡山八幡宮で発見された、天文17年(1548年)の木札だと言われています。
「神社の座主がとても厳しく、ついに一度も焼酎も与えてくれなかった」
宮大工と思われる人物が書いた文言ですが、16世紀中頃には焼酎が人々の間で親しまれていたことが想像できます。
当時大口市は人吉球磨を治めていた相良氏の領地でもあったのですが、相良氏は東南アジアを中心に活発に交易を行っており、そこから焼酎の製造技術が持ち込まれ、藩内で焼酎文化が広まっていったのではないかと考えられています。
なぜ球磨焼酎は“米”を使用するのか?

先述の通り、球磨焼酎の原料は“お米”です。人吉球磨地域の焼酎造りにおいて、これは基本的には16世紀頃から変わっていないと考えられています。
なぜ人吉球磨では焼酎造りにお米が使われ続けてきたのか。
当時はまだサツマイモが日本に伝来していなかったと考えられているため、そもそも芋焼酎を作ることができなかったというのが、一番の理由です。
また、比較的温暖な気候の人吉球磨地域は日本酒づくりにはあまり適していなかったという理由もあるようです。
焼酎造りの確立と規制強化
16世紀末、文禄・慶長の役では、秀吉軍に従軍した相良氏が朝鮮出兵に赴きました。
相良氏はこの際に、焼酎造りのノウハウを有する朝鮮人技術者を捕虜として捕らえ、連れ帰ったと言われています。
ここで蒸留法の新しい技術がもたらされたことで、江戸時代へと進んでいく中で米焼酎の文化が確立され、盛んに作られるようになっていきました。
一方江戸時代に入ると、米は幕府や藩にとって貴重な物資として認識されるようになるため、無許可での米焼酎の製造や販売は厳しく取り締まられました。
それでも、球磨の人々にとって焼酎を飲むことは大きな楽しみであり、焼酎の販売が認められる「入立(いりたち)」という許可を得た現代の居酒屋のような休憩所にて、米焼酎は飲まれ続けてきました。
入立のいくつかはやがて米焼酎を作るようにもなり、現在人吉球磨にある蔵元の中には入立から発展した施設もあるようです。
激動の時代を乗り越えた球磨焼酎の歩み
明治維新と焼酎文化の開花
明治時代に入ると、球磨焼酎は大きな転換期を迎えます。
江戸時代の厳しい酒造規制が緩和され、自由に焼酎が造れるようになったことで、球磨の蔵元は一気に活気づきました。
米焼酎を飲むことができる「焼酎屋」は、60件以上もあったといわれています。
また、この頃から原料に玄米ではなく白米を使用するようになり、さらに「二段仕込み」という製法も確立されます。これにより生産効率が改善され、米の豊かな風味がより引き出されるようになったため、球磨焼酎の品質は格段に向上しました。
戦争と復興、そして全国へと広がる球磨焼酎
大正から昭和、特に第二次世界大戦中、球磨焼酎の造り手たちは、原料や燃料の不足に苦しみながらも、その伝統の火を絶やさぬよう奮闘しました。
戦後の復興期には、焼酎造りに新たな技術革新がもたらされます。特に画期的だったのが「減圧蒸留法」の開発です。
これによってよりクリアでフルーティーな焼酎が造れるようになり、それまで焼酎を飲まなかった層にも人気が広がり、全国へと球磨焼酎の名が知れ渡る大きなきっかけとなりました。
そして、2000年代には国税庁から「地理的表示の産地指定」を受け、フランスのボルドーワインやコニャック、スコットランドのスコッチウイスキーなどと並び、世界に誇る「地名を冠するお酒」としての地位を確立しました。
これは、500年以上にわたる球磨焼酎の歴史と品質が認められた証です。長い歴史を経て、球磨焼酎は国内外で高く評価されるようになったのです。
球磨焼酎は世界に誇る地域の宝!

今回は500年以上の歴史を持つ人吉球磨の伝統的な地域資源、球磨焼酎の歴史について解説していきました。
長い期間を経て発展を繰り返してきた球磨焼酎は、今や世界に誇る地域の宝です!
ぜひ球磨焼酎が歩んできた歴史を想像しながら、毎日の晩酌をさらに充実したものにしていただけたらと思います。
このメディアサイトでは、他にも人吉球磨地域の魅力や特徴をご紹介しています。知りたいこと・気になることがあれば、いつでもこのサイトにお越しください!