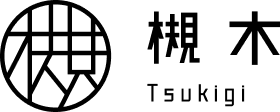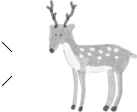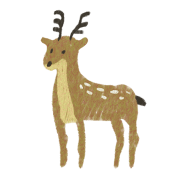人口減少やそれに伴う地域産業の衰退に悩む地方自治体にとって、地域活性化起業人の制度は、都市部の企業の力とノウハウを地域に取り込む革新的な一手です。
企業が従業員を派遣するという形で行われる従来の制度に加えて、2024年には「副業型」と呼ばれる制度も追加され、これまで以上に都市人材を受け入れやすくなりました。
専門知識や新たな視点を地域にもたらし、活性化の起爆剤となる可能性を秘めている地域活性化起業人。
本記事では、制度の概要から導入のメリット、事例紹介、類似制度との比較までを徹底解説。当制度の導入を検討されている自治体担当者様は、ぜひご覧ください。
地域活性化起業人ってどんな制度?

地域活性化起業人は、地方自治体が都市部の人材を受け入れ、そのノウハウや知識を活用して地域の活性化に取り組むという制度です。
似た制度に「地域おこし協力隊」や「地域プロジェクトマネージャー」というものがありますが、企業の人材を地域のニーズや課題などに合わせて高い自由度で採用、活用できるという点で異なります(詳しくは後ほど解説します)。
 地域活性化起業人の導入は、単なる人材不足の解消に留まりません。
地域活性化起業人の導入は、単なる人材不足の解消に留まりません。
都市部の企業にとっては、社員の新たな能力開発や社会貢献活動への参加を促す機会となり、地域にとっては、外部からの新たな視点や専門性が地域課題の解決や新たな産業の創出に繋がる大きな力となり得ます。
さらに2024年、地域活性化起業人には従来の「企業派遣型」に加え、「副業型」という新しい形態が追加され、これによりさらに柔軟かつ最適な人材の受け入れが可能になりました。
「企業派遣型」と「副業型」については、以下でさらに詳しく解説していきます。
企業派遣型

企業と自治体が協定を結び、受入自治体区域内での勤務日数が月の半分以上となるように勤務するというのが企業派遣型地域活性化起業人の要件です。
派遣期間中の経費については原則地方自治体が負担する必要がありますが、社員の給与等に関する経費については年間560万円/人等を上限に国が支援することになっています。
副業型

個人(※)と自治体が協定を結び、月4日以上かつ月20時間以上勤務するルールで行うのが副業型地域活性化起業人。最低でも月に1日は受入自治体内で勤務をする必要がありますが、それを満たせば自治体外での業務も勤務時間としてカウントされます。
副業期間中の経費についてはこちらも原則地方自治体が負担することになっていますが、報償費等上限100万円/人、旅費上限100万円/人の、合計200万円までは国が支援するルールです。
※企業に所属している個人と契約を結ぶこともありますが、あくまで企業と自治体間ではなく、個人と自治体の間で結ぶ契約となります。
企業派遣型と副業型の内容比較
| 主な連携主体 | 地方自治体 ⇔ 企業 | 地方自治体 ⇔ 個人 |
|---|---|---|
| 活動方法 | 企業に在籍したまま一定期間自治体に派遣され活動する |
個人のスキルや経験を活かし本業を持ちながら活動する
|
| 期間 | 6か月以上、3年以内 | |
| 活動スタイル | 期間中は地域活動に一定以上の時間を割く |
本業とのバランスを取りながら地域活動に取り組む
|
| 求められるスキル | 企業の組織力、専門知識、ノウハウ、ネットワークなど |
個人の専門スキル、経験、人脈など
|
| 制度の種類 | 企業派遣型 | 副業型 |
地域活性化起業人を導入するメリット

地域活性化起業人の導入は自治体に様々なメリットをもたらします。ここではその一部をご紹介します。
専門知識・ノウハウの導入
企業の専門的な知識や最新ノウハウを地域に取り入れることができ、既存の取り組みの加速が期待できます。例えば、マーケティングの専門家による地域産品の販路拡大支援や、ITエンジニアによる業務効率化などがあります。
新たな視点と発想
外部からの人材は、これまでにない新しい視点や発想を地域にもたらすかもしれません。固定観念にとらわれない自由な発想は、地域資源の新たな活用方法や観光客誘致の斬新なアイデアなどに繋がる可能性があります。
地域内外のネットワーク
派遣された人材の派遣元である企業や自身が持つネットワークを地域でも活かすことができます。これにより新たなビジネスパートナーシップの構築や地域産品の販路拡大、情報発信力の強化など、地域内外との連携を深めることができます。
職員の意識改革とスキル向上
地域活性化起業人との協働は、自治体職員にとって新たな刺激となり、意識改革やスキル向上に繋がります。また、プロジェクトマネジメント能力やコミュニケーション能力といった総合的な能力の向上も期待できます。
地域活性化起業人の導入事例

令和5年度時点で、地域活性化起業人は779名、活用自治体は449団体、派遣企業は330社と、いずれも過去最高を記録しているとのことで、導入事例も豊富に集まってきました。
大企業を誘致して最新のノウハウを導入しDX化や商品開発などを推進している事例や、ベンチャー企業のスピード感とアグレッシブさを取り入れて地域内外を活性化させている事例など、その内容は多岐に渡ります。
ここでは具体的な事例の内容は紹介しきれませんが、総務省が令和5年度の地域活性化起業人の具体的な活用事例を紹介しているので、ぜひ一度ご覧いただけたらと思います。
※事例紹介は13ページ目からとなっています。
類似制度との違いを比較

地域活性化に関する制度としては、地域活性化起業人の他に「地域おこし協力隊」や「地域プロジェクトマネージャー」といった制度もあります。どれも似た制度だと思われるかもしれませんが、それぞれの制度は雇用形態や参加条件などに違いがあります。
地域おこし協力隊は、「都市部から過疎地域などの条件不利地域に移住して、地域活性化のための活動を行う制度」です。地域活性化起業人の内容と同じ部分が多いですが、地域おこし協力隊は雇用主が地方自治体による直接雇用である点や、現地に移住して勤務をするという勤務形態において異なります。
また、参加条件は地域の公募に自ら応募する必要があるという違いもあります。
地域プロジェクトマネージャーは、「地域・行政・民間・外部の関係者をつなぎつつ、実質的にプロジェクトをマネジメントする人材を受け入れる制度」です。条件や雇用関係は地域おこし協力隊に似ていますが、自治体が「重要プロジェクト」と位置付ける、より規模が大きく高度な業務を担うことが特徴です。
これらの制度と「地域活性化起業人」との主な違いを表にまとめたので、ぜひご覧ください。
| 地域活性化起業人 | 地域おこし協力隊 | 地域プロジェクトマネージャー | |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 企業のノウハウ等を活用した地域活性化 | 地域への移住・定住促進と地域活性化 | 重要プロジェクトの推進、課題解決 |
| 対象となる人材 | 都市部の企業に所属する社員、または専門スキルを持つ個人 | 都市部在住で、地方への移住・定住を希望する個人 | 専門的な知識・経験を持つ個人 |
| 活動形態 | 企業派遣型、副業型 | 地域に居住し、地域活動に従事 | プロジェクト単位での業務委託、または雇用契約 |
| 報酬・待遇 | 自治体、企業、個人の契約による | 自治体から報酬が支給(生活支援金等) | 自治体から委託費または給与が支給 |
| 企業との連携 | 企業派遣型:必須 副業型:連携する場合あり |
基本的に無し | 連携する場合あり |
「地域活性化起業人」で地域を新しい視点で盛り上げる!
今回は地域活性化に関する制度である「地域活性化起業人」についてご紹介しました。
地方の人材が都市部へと流出している現状がある以上、最新のノウハウや技術も都市部に集まってしまっているのは事実です。
ですがこの制度を活用することで、都市部の人材を地方でも受け入れることができ、活性化を推進するきっかけになるかもしれません。
近年は都市部人材の地方への関心も高まってきているので、ぜひこの機会に制度の活用を検討してみてください。
当サイトでは他にも地方創生に関する様々な記事を発信しています。ご興味がございましたら他の記事もご覧ください。