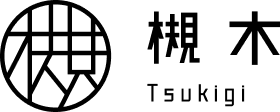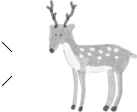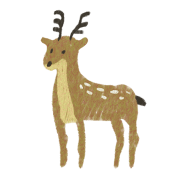広大な面積で栽培されるお米は、現在機械を使って大量に、短時間で刈り取られ、効率よく商品へと加工されていきますが、昔は当然機械などなく、全て手作業で行われていました。
「昔ながらのやり方に挑戦し、お米のありがたみとお米本来のおいしさを実感したい!」
この想いのもと、今回はお米栽培の大先輩に教えを請いながら、実際に手作業での稲刈りに挑戦してきましたので、その様子や具体的な手順などについて解説していきます。
便利な時代に、あえて手作業で稲刈りをする意味

現代はとても便利な時代です。お米作りの世界においても、道具や機械は年を追うごとに新しいものが生まれ、非常に快適に、効率よく、そして高いクオリティのお米が栽培できるよう日々進化しています。
新しい技術で現状がよりよくなるのはすばらしいことなのですが、一方で簡単に美味しいお米が作れるようになったことで、食や毎日の暮らし自体への感謝の気持ちが少しずつ失われてきているように感じています。
毎日おいしいお米を食べることができている状況は、非常にありがたいことです。今回はその気持ちを思い出し、農家の方や毎日の平和な生活に改めて感謝するために、あえて昔ながらの手作業での稲刈り体験をしてきました。ここではまず、あえて手作業で稲刈りをする意味や目的、魅力などについてご紹介していきます。
お米のありがたみを実感できる
やはり、手作業で行う稲刈りは機械で行うよりも大変です。たくさんの稲を刈り、多くのお米を生産するためには、大変な手作業を長時間かけて行う必要があります。
この大変で過酷な作業を体験し、乗り越えることで、改めて毎日食べている美味しいお米に、そしてそのお米を生産しているお米農家の方々に対して感謝の気持ちを抱くことができます。
「私は普段から農家さんに感謝しているよ~」という方もいると思いますが、これまでに農作業の体験をしたことがないなら、この大変さを知ることで感謝の気持ちはより大きくなると思います。
全員が農家さんに対して敬意を払うべきだ!と強制するつもりはありませんが、感謝の気持ちを実感することで、毎日の食事がより豊かで幸せな時間になると思うので、ありがたみを知ることはとてもおすすめです。
より美味しいお米が出来上がる

手作業で稲刈りを行うことで、より美味しいお米が出来上がるとも言われています。
これは感謝の気持ちを持つことでより美味しく感じられる、という精神的な理由もあるのですが、手作業で丁寧に稲刈りを行うことで、お米の美味しさをより引き出すことができると考えられているからです。
「お米の美味しさをより引き出すことができる」というのは、主に稲刈りの後の乾燥工程が関係しています。稲刈り後の乾燥工程を手作業で行うことを稲架掛け(はさがけ、詳細は後述)と言いますが、このやり方では太陽の光をじっくり浴びてゆっくりと乾燥されるため、お米の旨味が粒に凝縮されると考えられています。
実際に食べてみても、その違いが分かるくらいお米の味がしっかりと感じられて、非常に美味しいです。
「稲架掛けで乾燥させたお米を食べてみたい!」という方は、当サイトでそのお米を販売していますので、ぜひ購入して食べてみてください。

そもそも機械を使うことが難しい
機械を使わない理由としては、そもそもその農地で機械を使用することが難しいという理由も挙げられます。
今回僕が稲刈りの体験をさせてもらったつきぎ集落は、熊本県の山奥の秘境にあります。このエリアでは、まず山奥なので田んぼがいびつな形をしていることが多く、稲刈り機やコンバインが上手く使えないという場合が多くあります。また乾燥機についても、大規模農家がいないこのエリアでは乾燥機を所有している人はおらず、また町の共同乾燥機までも距離が非常に遠いため、現実的ではありません。
そのため、つきぎ集落のような平地ではない田んぼでお米を栽培する農家さんは、使いたくても機械を使うことができないという事情もあるのです。
手作業での稲刈りの手順を解説!

それでは、ここから手作業で稲刈りを行う際の手順や使用する道具、注意点などについてご紹介していきます。今回は熊本県球磨郡多良木町にある「つきぎ集落」という地域で長年お米栽培を行われている椎葉さんにご協力いただき、体験をさせていただきました。
お米栽培の大先輩にやり方を丁寧に教わりながら体験してきたので、これから始めて手作業で稲刈りを行うという方は、ぜひ参考にしてみてください。
手作業での稲刈りの手順は、以下の通りです。
- 適切な時期を見定める
- 必要な道具を用意する
- 鎌で稲を刈り取る
- 刈った稲を束ねる
- 落穂拾いをする
適切な時期を見定める

刈るのに適した稲の状態。黄金色の稲穂が特徴です。
1つ目の工程ですが、これが一番重要だと言っても過言ではありません。稲刈りは適切な刈り時を見極めて行わないと、最終的なお米が美味しくないものになってしまう可能性があるからです。
適切なタイミングを見定めるポイントは、日数で考えると穂が出てから約40~45日くらいだと言われています。ただし、最近は気候変動の影響が深刻で、40日以前が適切だったり、逆に45日以降が適切だったりと、不安定な年が続いています。
そのため、適切なタイミングは日数ではなく稲穂の状態を確認するのがおすすめです。稲穂が黄金色に色づき、下に垂れ下がるタイミングが最適だと言われています。
上記画像を参考に、一番好ましい刈り時を見極めましょう。
必要な道具を用意する
稲刈りの時期が決まったら、作業に必要な道具を準備しましょう。
稲刈りは鎌や長靴などを用意して行います。稲刈りは通常の道具を使用してもできるにはできますが、田んぼ作業には田んぼ作業用の道具が販売されています。これらを使うことで効率よく作業を行うことができるため、田んぼ用のものがある道具については、そちらを選んで準備するのをおすすめします。
用意する道具一覧をざっとまとめてみました。
| 鎌(のこぎり鎌) | 稲を刈るのに使用。一般的な草刈り鎌ではなく、専用ののこぎり鎌がおすすめ。 |
|---|---|
| 長靴(田植え長靴) | ぬかるんだ田んぼを歩く際に必須。どの長靴でも問題はないが、より快適に作業を行うためには田靴(田植え長靴)がおすすめ |
| 手袋 | 作業効率を上げるのと、手を保護するために使用。 |
| 長袖の服 | 皮膚を保護するために必須。肌が露出していると、ワラが当たって肌荒れを起こしやすいため、要注意。 |
| 長ズボン | 皮膚を保護するために必須。肌が露出していると、ワラが当たって肌荒れを起こしやすいため、要注意。 |
| ベルト | 鎌を使用していないときも、ベルトを使うことで携帯できる。 |
| ひも(もしくは昨年のワラ) | 刈った稲を束にする際に使用。お米農家は昨年の稲刈りで出たワラを保存しておいて、その年の紐代わりに使用することが多い。ワラは耐久性が高く、またそのまま土に捨てても問題ないため、エコでもありおすすめ。 |
鎌で稲を刈り取る

ここでようやく、稲刈りのメインイベント、刈り取りを行います。
やり方はシンプルです。まず鎌でひっかけて稲をまとめ、その束を空いている手で掴み、稲の根元から4,5cmほど上のあたりに鎌を入れ、刈り取ります。この時に注意するのは、鎌を持っていない手で稲を掴む時は外側から掴むということです。内側から掴むと親指が下になり、刈り取る時に親指を切ってしまう可能性があるため大変危険です。
そして、乾燥機を使用せず稲架にかけて乾燥させる際には、刈り取った根本が揃った状態で乾燥させる必要があるため、鎌はまっすぐ動かすことを意識し、斜めに刈らないように注意しましょう。
この作業は基本腰を曲げた状態が続くので、足腰へのダメージがとても大きかったです。まだ若い方も油断せず、気合を入れて取り組みましょう!
刈った稲を束ねる

刈った稲は10〜12株分で1つの束にして括ります。3〜4本のワラで稲の根本付近を1周させてワラを引っ張り、そしてねじりながら締めることで固定することができます。
一見簡単そうに見える作業ですが、ワラを使って束を使うやり方は想像以上に難しいです。今回のようにお米栽培の大先輩がいると教えてもらいながらやることでできるようになりますが、そういう方がいない場合はワラを使うやり方には苦戦するかもしれません。
もし不安な場合は、市販の紐を使うことで比較的簡単に束を作ることができます。
落穂拾いをする
稲刈りは刈って束を作って終わり、ではありません。刈り終えた田んぼ一面を見渡してみると思いのほか刈り切れていない稲がぴょんぴょんと残っています。また、束を作る際に抜け落ちてしまった稲穂が落ちていることもよくあります。
お米のありがたみ、感謝の気持ちを実感するために手作業での稲刈りに挑戦したなら、残ってしまった稲穂もすべて回収しておきたいところ。
一見地味な作業ですが、黙々と拾うのにハマる人もいて意外と楽しいですよ。
手作業で稲刈りを行う際の注意点

刈る足場が悪い田んぼでは、ぬかるんだ地面に足がとられ、長靴が脱げてしまうことも(笑)
ここまでで稲刈りを手作業で行う手順をご紹介しましたが、合わせて注意点、気を付けるポイントについてもご紹介します。
まず、田んぼの地面は水分を多く含んでおり、ぬかるんでいます。乾き具合によっては、足が抜けなくなるほどぬかるんでいることもあるため、バランスを崩して転んでしまわないよう、注意してください。
コツは、刈り終えた後の稲の株を踏んで歩くことです。株は固く安定しているため、足をとられることはありません。
また、田んぼの中に潜む生き物にも注意してください。基本的には害がある生き物はそれほど多く生息していませんが、まれに痒みを引き起こす毛虫がいたり、毒を持ったマムシが飛び出してくることがあります。
正直生き物に対して万全な状態で対策するのは難しいですが、長袖長ズボンで肌の露出をなくすことは必ず徹底してください。
稲刈りのあとも手作業で

刈り終えた後の稲穂は、乾燥させて食べられる状態へと加工します。
この乾燥工程は、現在多くの農家では機械を使って行っていますが、乾燥機がない、または町の共同乾燥機が近くにないという理由で今でも機械を使わず、人力と自然の力で乾燥させるお米農家さんはたくさんいます。
また、お米は木や竹で組んだ稲架(はさ、お米を掛けるための柱)を使って天日干しをすることでお米の旨味がさらに引き出されるとも考えられているため、より美味しいお米にするために、あえて稲架掛けを行う農家さんもいます。
今回稲刈りを行ったつきぎ集落では、上記の両方の理由で、現在でも機械を使わない稲架掛けで乾燥工程を行っています。こちらもまた大変な作業ですが、乾燥し終えた新米の味は、たしかに感動するくらい美味しかったです。
自分の手で刈り取ったお米は一番美味しい!

今回は手作業で稲刈りを行う際の手順や必要な道具、注意点などについて解説していきました。
稲刈りを手作業で行うのはやはり大変で、作業を終えた後はもうバテバテでした。でも、大変な作業に取り組んだからこそ感じる、農家の方への感謝の気持ちや、お米一粒一粒を大切に食べようとする想いなどが強く芽生えてきて、とても良い経験になったなと感じました。
また、稲刈りをして乾燥させた後の新米を食べてみたのですが、やっぱり自分たちで収穫したお米は本当に美味しかったです。天日干しの影響も大きいと思います。
ぜひみなさんにもこの体験をしていただきたいなあと、心から思います。
もし、まだ稲刈りを手作業でやるか機械を使うかで悩んでいるなら、一度当サイトが販売しているつきぎ米を食べてみていただきたいと思います。こちらは稲刈り工程は機械を使っている部分がありますが、乾燥工程については全て手作業で、天日干しによって行っています。
自然乾燥ならではの美味しさも体感していただけると思いますので、ぜひ一度試していただき、手作業で行う魅力を体験していただきたいと思います。